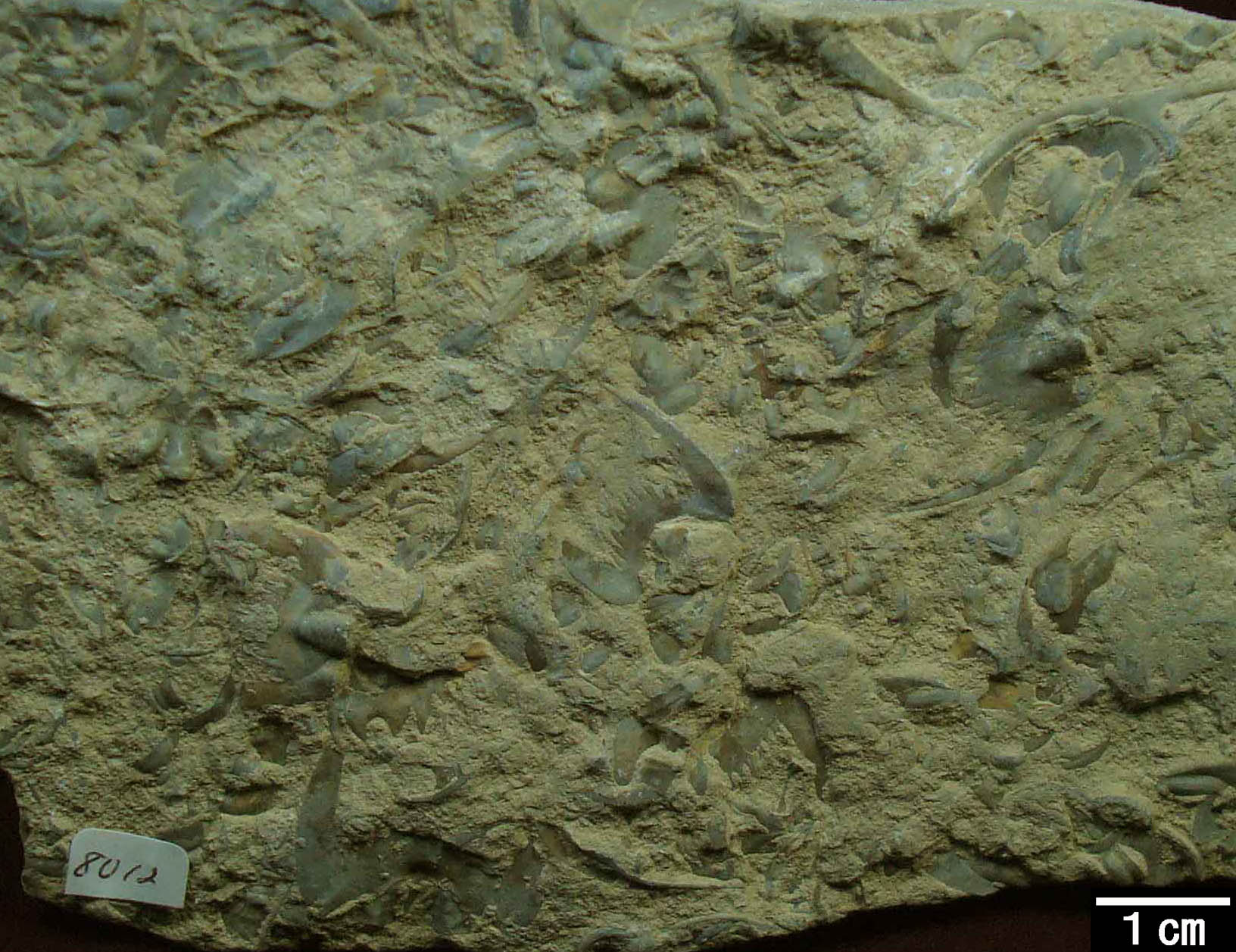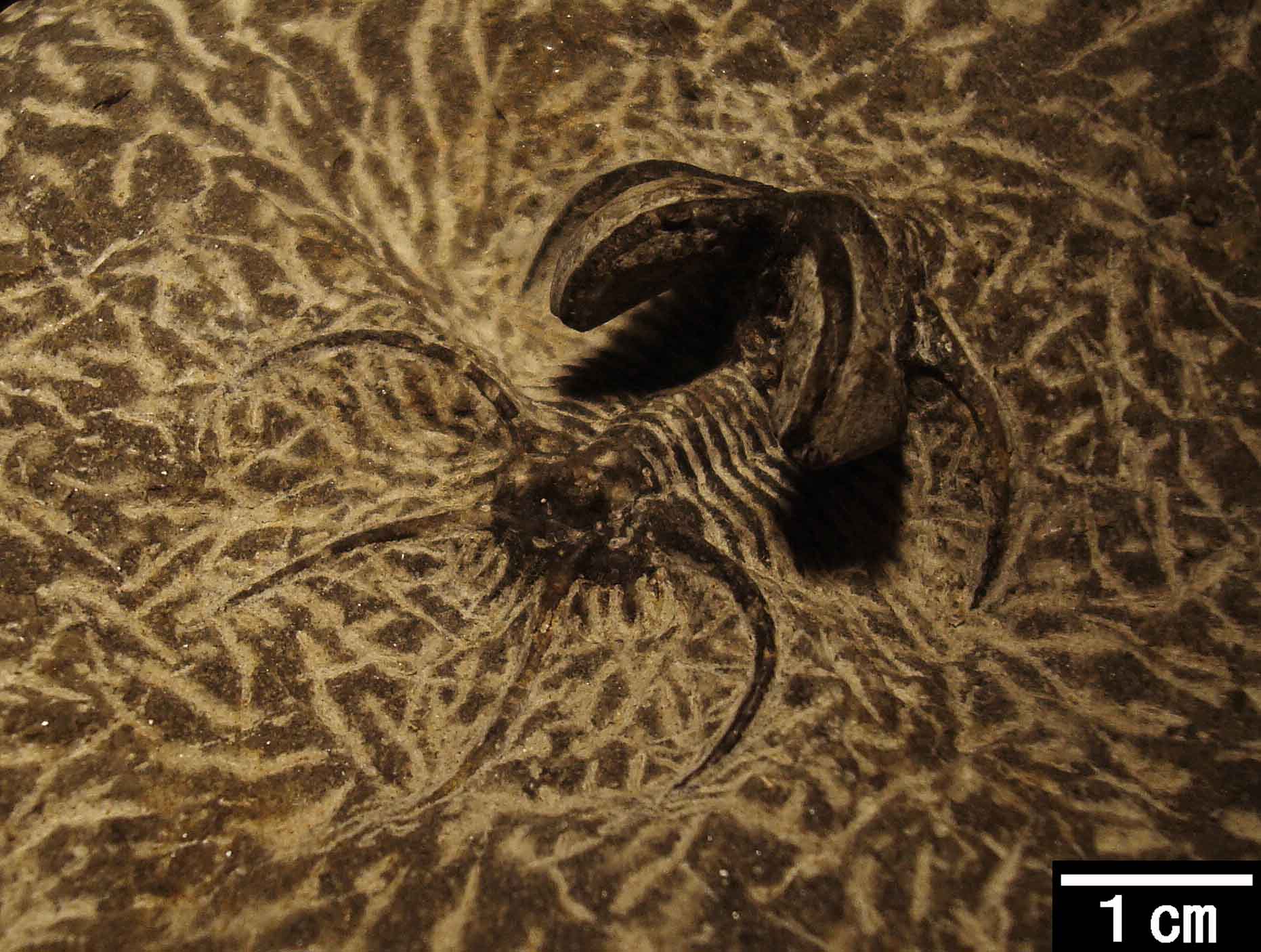| 三葉虫類の例 |

アメリカ産
|

朝鮮半島産
化石になった後に起きた地殻変動で体全体が変形している。
|

エオダルマニチナ Eodalmanitina sp.
三日月形の複眼をもつ。化石になった後に起きた地殻変動で体全体が変形している。
古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) ポルトガル
|
エルラシア Elrathia sp.
古生代初期の三葉虫で,尾部が小さい。アメリカ ユタ州のものが世界的に有名だが,遠く離れた朝鮮半島でも産し,このことは当時の分布域やその後の大陸移動の状況を示す。
古生代カンブリア紀(5億4100万年〜4億8500万年前) 左:アメリカ産,右:朝鮮半島産
|

セラウルス,フレキシカリメネ Ceraurus pleurexanthemus, Flexicalymene
senaria
2種の三葉虫の共生標本。頭部・尾部から長い棘が出ているのがセラウルス。もり上がった丸い頭部をもつものがフレキシカリメネ。
古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) カナダ
|

イソテルス Isotelus maximus
大型の三葉虫の仲間で,体長は30cmに達するが,殻の厚みは1mm程度しかない。
古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) アメリカ
|

アサフスの仲間 Asaphus (Neoasaphus) kowalewskii
眼が伸びており,泥に潜って周囲をうかがったと思われる。
古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) ロシア
|
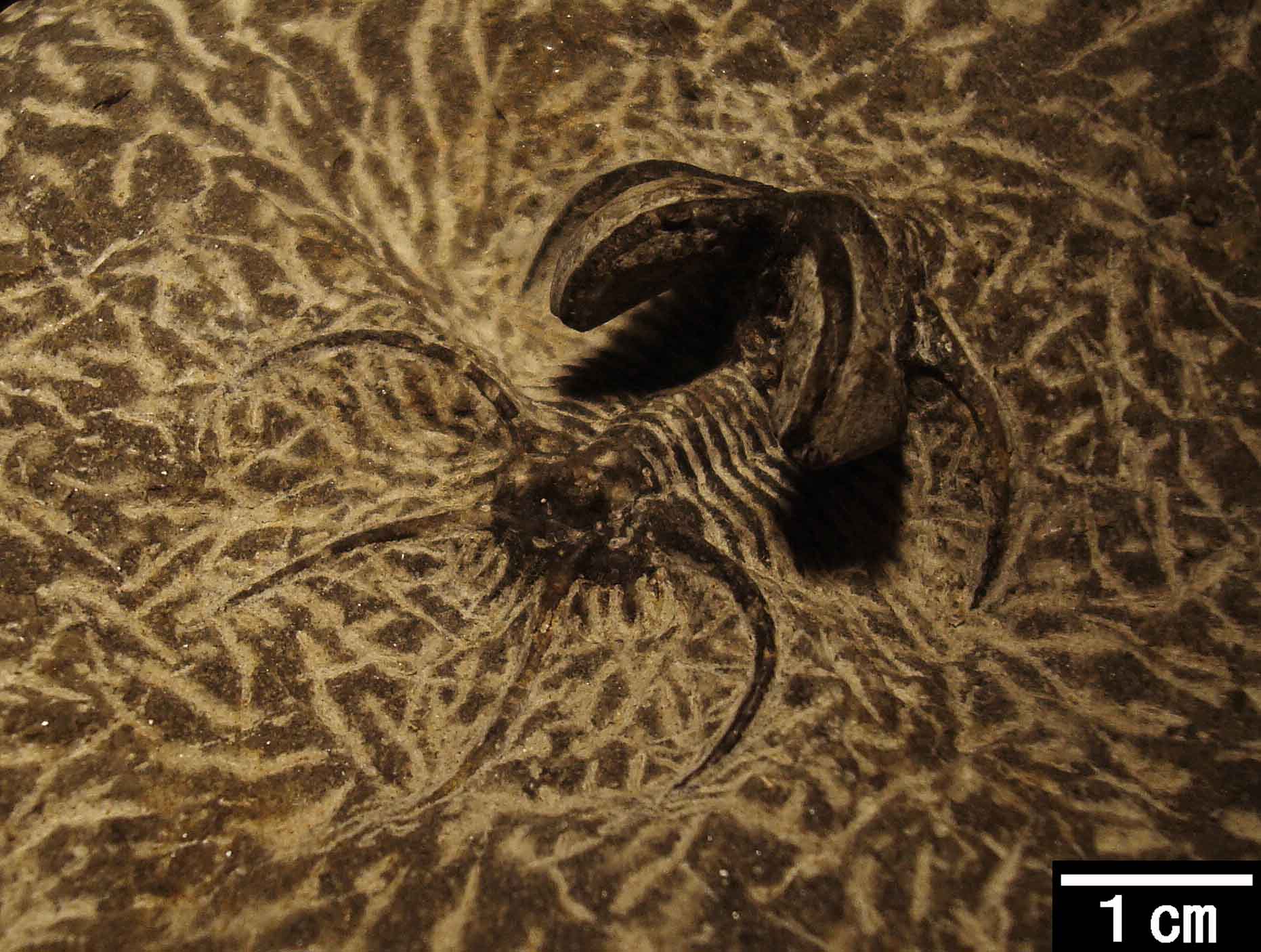
 |


|

ドロップス Drops armatus 三葉虫類
棘が多い奇怪な三葉虫。昆虫と同じような細かい複眼構造がある。
古生代デボン紀(4億1900万年〜3億5900万年前) モロッコ |
デボン紀の三葉虫類
古生代中頃のデボン紀になると,このように棘が多かったり,尾版が大きい奇怪な三葉虫が多く出現してくる。棘は外敵からの防御のためと考えられている。赤矢印先には複眼構造が見える。
古生代デボン紀(4億1900万年〜3億5900万年前) モロッコ |